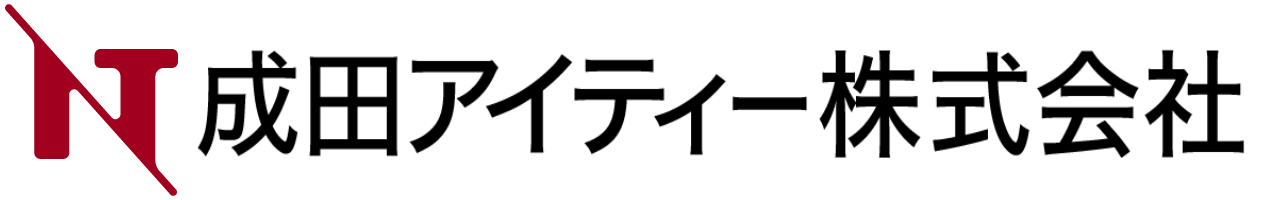「最近の若い者は…」なんて言い出すと、周りからはすっかり『おっさん』扱いされたりします。真偽の程は分かりませんが、エジプトの壁画にもそんなことが書いてあった、なんて話も聞いたことがあります。
でも、年配者の理解が及ばないことを若者が成し遂げることによって、世の中はここまで来たんだろうなと思うわけです。
最近よく聞くお話しから
「言われたことしかやらない」
「新しいこと、挑戦的なことを頼むと、嫌な顔をする」
といった、部下の方に対する評価です。
部下の側からは、
「面倒なこと頼まれた」
「やっても評価されないし、給料上がるわけでもないし」
「残業が増えるだけ」
なんて言葉が聞こえてきます。
これは、何のために仕事をしているのかという問いに対して、上司と部下の間でのギャップが生じていることに起因しているように思います。
能力のある方や新しい環境で挑戦したいという方ならば、待遇の満足するところに転職するのがベストですw。それも、できるだけ早い方がいいです(笑)。
一方、文句言いつつも会社に残っている社員の方には、ちゃんと働いてもらわないと困ります。部下の方にしてみても、同じ働くなら楽しかったり、やりがいを感じる方がいいに決まっています。
このような悩みは国を問わず、時代を問わずあるようで、学問として研究されています。これを「モチベーション理論」と言います。
モチベーション理論とは?
文献によると、モチベーション理論は1950年代から発展したそうです。それによると、
- 人は何によって(What)動機づけされるのか?
- 人はどのように(How、Why)動機づけされるのか?
に大別されます。
Ⅰ.で有名なものに、マズローの欲求段階説というのがあります。人間の欲求は低次から高次にかけて以下の5段階があるとされます。
- 生理的欲求
- 安全の欲求
- 所属と愛の欲求
- 尊重の欲求
- 自己実現の欲求
詳細は割愛しますが、仕事に関して言えば3~5の辺りが満たされることでモチベーションが上がる、すなわちやりがいを感じるということになりそうです。つまり、
- 自分の居場所と言える会社に在籍して
- 会社の上司、同僚、部下から慕われ
- 周りから頼られながら、自分が楽しく感じる仕事をやれている
ということで、モチベーションが上がるのではないか、ということです。
Ⅱ.についても色々な理論があるのですが、大まかにいえば「期待と報酬のバランス」ということかと思います。
ここで言う期待とは、自分はこういう仕事をしたい、とか、この仕事ならこれ位給料もらえそう、とかいうことでしょうか。
一方報酬は、提示された仕事の内容や責任の重さ、裁量の大きさであったり、給料や休み等の待遇ということになろうかと思います。
前項で書いたような不満や文句は、Ⅰ.の動機づけが明確でなく、Ⅱ.の期待と報酬のバランスがよくない、ということになるかと思います。もちろんⅠ、Ⅱどちらかが満たされない場合もあれば、両方とも満たされていないこともありえます。
モチベーション理論から考える教育とは

Ⅰ.人は何によって(What)動機づけされるのか?
を強化するのに役立ちそうです。
教育の方法にはOJTや集合研修等ありますが、例えば英語でTOEIC700点をとるために英語の研修を受けさせる、ということがあります。
これは、TOEIC700点を取ることによって仕事でどういうことに役立つのか、本人にとってどういうメリットがあるのかが明確でないと、モチベーション向上にはつながりづらいということになります。
つまり、とりあえず研修受けさせて、あとはそれを仕事に役立たせるのは本人次第、研修を役に立てられないのは研修を受けた本人の能力が低い、なんて考えているようではお金をドブに捨てるのと一緒、ということになります。
モチベーション理論から考える報酬とは

Ⅱ.人はどのように(How、Why)動機づけされるのか?
にひもづくように思います。
まずは「仕事のやりがい」という観点から考えてみます。
これは、ある程度の経験と能力がある社員の方に言えることだと思いますが、本人の意思に関係なく指示された仕事をしているだけの場合は、やりがいとは全く無関係。
つまり、本人の期待に対する報酬は「0」ということになりそうです。
「期待に対する」報酬ということになるので、本人の期待を確認するという作業は必要ではないか、それに対してどのように仕事をしてもらうか、ということが大事そうです。
次に物理的な報酬、つまり賃金や休みです。
これらは入社時に提示した内容に納得して入社し、かつ実際の待遇がその通りであれば、特に問題は起こらなそうです。逆に言えば、入社前に細かいレベルまでお互い納得するまで確認しておけば、すぐに問題にはならないように思います。
しかし、最近はSNSやWebでの情報収集が容易になったので、若い社員ほど他社の情報を容易に、かつ大量に得ています。よって、やりがいについても賃金についても、より魅力的なところがあれば、すぐに転職してしまうという可能性があります。
また、自社が「ブラック」だと認識されてしまった場合は、一斉に社員がいなくなる可能性もあります。
ですので自社の社員が考える、現在の「期待」と「報酬」のバランスがどうなっているのかは常に把握しておく必要がある、と言えると思います。
まとめ
それこそが上司や経営に携わる方の大事な仕事であると思います。
結局ありきたりな結論になってしまうのですが、
- 上司と部下のコミュニケーションが大事
- 上司は、部下に対して一方的な指示をするだけではダメ
- 多少難しいかな?と思われることも、裁量と報酬をきちんと提示して話し合った上でトライしてみましょう
- 教育は、目的を認識させてから受けさせましょう
- 上司もアンテナを広げて、情報をアップデートしましょう
ということではないでしょうか。
それによって社員本人も会社も、次の段階へのステップアップを継続できるようになるんだと思います。